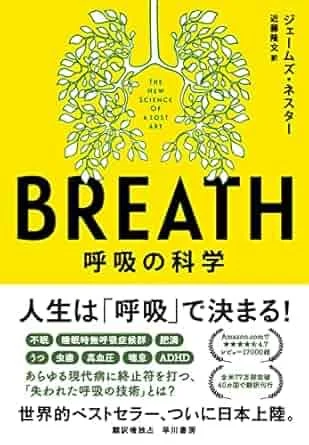【書籍紹介】呼吸(BREATH)
こんにちは、AKIです。
前回の記事では、ピラティスにおける呼吸法(特に胸式呼吸やインナーユニットとの関係)について掘り下げましたが、今回はもう一歩踏み込んで、「呼吸そのものの本質」について考えてみたいと思います。
現在、私は育児休業中で思うようにエクササイズの時間を取ることが難しい日々が続いていますが、そんなときこそ呼吸に意識を向けることが、体と心のバランスを保つ支えになってくれています。
今回ご紹介するのは、サイエンス・ジャーナリストのジェームズ・ネスター著『呼吸(BREATH)』。
この一冊には、古代の呼吸法から最新の科学的知見まで幅広い内容が詰まっており、読むだけで呼吸に対する見方がガラッと変わります。
「呼吸ってそんなに大事なの?」と思う方こそ、ぜひ手に取っていただきたい。
エクササイズができない日でも、“呼吸”は今日から変えられる。
そんな気づきが得られる本です。
本の概要:なぜ「呼吸」が人生を変えるのか?
ジェームズ・ネスター著『呼吸(BREATH)』は、「呼吸こそが現代人の健康課題を解決する鍵である」という視点から、科学と歴史、実体験を交えて呼吸の本質に迫る一冊です。
本書の冒頭でネスター氏はこう問いかけます。
「私たちは一日に2万〜3万回呼吸しているが、その呼吸、正しくできているか?」
この問いをきっかけに、彼は呼吸をめぐる壮大な探求に出かけます。
主な内容紹介
人類の進化と呼吸の退化:
現代人の呼吸器系は退化している? 鼻呼吸を忘れた文明が招いた健康問題とは。鼻呼吸 vs 口呼吸:
口呼吸は口腔崩壊・酸素摂取効率の低下・自律神経の乱れなど、多くの健康リスクに直結。鼻呼吸こそが本来の自然な呼吸法であることを、科学的に裏付けていく。古代の呼吸法と最新科学の融合:
インドのプラーナーヤーマ、中国の氣、チベットのツンモ呼吸など、古代の叡智がどのように現代の呼吸法として応用できるのかを実践を通して検証。呼吸と身体・精神の相互作用:
呼吸ひとつで血圧が下がり、心拍数が整い、ストレスホルモンの分泌が変わるという、“意識する呼吸”がもたらす生理的・心理的変化をわかりやすく解説。
この本は、単なる健康本でも自己啓発書でもありません。
「人はどうやって呼吸すべきか」というシンプルでありながら深淵な問いに、科学・歴史・個人体験の3方向から真正面から向き合った、まさに“呼吸の教科書”ともいえる一冊です。
印象に残ったポイント:「吐くことの大切さ」と二酸化炭素の再評価
本書を読んで最も心に残ったのは、「呼吸は“吸う”より“吐く”が重要である」という考え方でした。
こちらは、前回のピラティスの呼吸ブログ記事と通じる内容になります。
これまでも感覚的には大切だと感じていたものの、今回改めてその背景にある体のメカニズムを知ることで、「なぜ吐くことが重要なのか」がより明確になりました。
■ 呼吸とは、“吐いてこそ”整う
本書では、呼吸の質は「どれだけ吸えるか」ではなく、「どれだけゆっくり、深く吐けるか」で決まると繰り返し説かれています。
ゆっくりと呼気を続けることで、副交感神経が優位になり、心身がリラックスした状態へと導かれる
息を長く吐くことで横隔膜や体幹(インナーユニット)の筋肉が自然と働き、安定した姿勢が保たれる
このアプローチは、まさにピラティスの胸式呼吸の原則と重なります
ピラティスでは、吐くことでお腹が引き締まり、背中側の肋骨の動きが出やすくなります。
これは単なる筋トレではなく、呼吸と動きが連動する統合的なトレーニングであるということを、身体で理解できた気がしました。
■ 呼吸により排出するCO₂は“不要なもの”ではない
さらに印象的だったのは、二酸化炭素(CO₂)の再評価です。
これまで「なるべく吐き出すべき老廃物」として扱われてきたCO₂が、実は私たちの健康にとって非常に大切な役割を果たしていることが、丁寧に紹介されていました。
「ボーア効果(Bohr effect)」:CO₂の濃度が高まることで、ヘモグロビンが酸素を手放しやすくなり、末端組織に酸素を届けることができる
CO₂が少なすぎると、酸素を抱え込んだまま放出されず、細胞レベルで“酸欠”状態になる可能性もある
その結果として、酸化ストレスや慢性疲労の原因になることも
つまり、呼吸において大切なのは「たくさん吐く」ことではなく、“ゆっくりと吐く”ことで適切なCO₂濃度を保つことなのだという点が、自分の中で大きな発見でした。
■ ピラティスの呼吸と科学の接点
ピラティスでは「吐きながら体幹を安定させる」呼吸法を実践します。
本書を読んでから、この呼吸法には呼吸生理学的にも確かな意味があるのだと納得できました。
呼気をコントロールすることで、副交感神経を優位にし、集中力が高まりやすくなる
横隔膜の適切な動きがCO₂の調整にもつながり、酸素の供給効率が上がる
こうした仕組みが、レッスン後のすっきり感や頭のクリアさにもつながっているのだと実感しています
ピラティスで実践する「呼気を意識した呼吸法」は、単なる筋肉の動きをサポートするためのものではありません。
呼吸を通じて自律神経が整い、ガス交換(酸素と二酸化炭素のバランス)が最適化されることで、身体の安定性と集中力が高まり、さらには思考や感情のバランスにも好影響を与えると考えられています。
つまり、呼吸は身体と心をつなぐハブ(接点)のような存在。
意識的な呼気を習慣にすることで、身体の動きだけでなく、精神面でも深い安定感を得られるのです。
どうしても落ち着かない時に ― 片鼻呼吸のすすめ
仕事や家事、育児に追われて、自分の心を整える時間すら持てない日もあります。
体を動かす余裕がない、けれど何かが引っかかるように落ち着かない。
そんなとき、わずか1分でも心をリセットできる方法があります。
それが、本書でも紹介している片鼻呼吸(ナディショーダナ)と呼ばれるシンプルな呼吸法です。
「自律神経のスイッチ」を整える
私たちの体は、交感神経(緊張・興奮)と副交感神経(リラックス・回復)がシーソーのようにバランスを取っています。
ですが、忙しさやストレスが続くと、このバランスは簡単に崩れてしまいます。
朝から緊張モードが続き、夜になっても頭が冴えて眠れない…。
そんなとき、意識的に呼吸を整えることが、自律神経の切り替えに大きな助けとなるのです。
実践:片鼻呼吸のやり方
静かな場所で、背筋をすっと伸ばして座ります(椅子でも床でもOK)。
右手を顔の前に持ってきて、親指で右の鼻を軽くふさぎます。
左の鼻からゆっくりと息を吸います(4秒ほど)。
吸い終えたら、右手の薬指で左の鼻をふさぎ、右の親指は鼻閉じたまま息を止めます(4秒ほど)。
右手の親指を外し、右手の薬指で左の鼻を閉じたまま、ゆっくりと息を吐きます(6〜8秒)。
今度は右の鼻から吸って、左の鼻から吐く。
これを1セットとし、5回〜10回ほど繰り返してみましょう。
※できる範囲でOK。無理に深く吸わず、吐く方を少し長く意識するのがコツです。
なぜ“片鼻”なの?
鼻には、実は「左右交互に空気が通りやすくなるリズム」があります。
このリズムは自律神経と関係しており、
右の鼻で呼吸すると交感神経(活動)
左の鼻で呼吸すると副交感神経(休息)
が刺激されると考えられています。
片鼻ずつ呼吸することで、このバランスを自然なかたちで整えることができるのです。
たった1分で、自分に戻る
片鼻呼吸は、特別な道具も場所もいりません。
どこでも、誰でも、たった1分で始められます。
子どもが寝たあとの静かな夜
イライラした時にトイレの個室で
忙しい朝に、立ったままでも
なかなか眠れない夜に
大事な会議やプレゼンの前に
そんな瞬間に、そっと自分の呼吸に意識を向けてみてください。
今ここに戻ってくる感覚が、きっと感じられるはずです。
まとめ|呼吸を整えることは、思考と行動を整えること
「呼吸が変わると、思考が整い、行動が変わる」。
これは単なるスローガンではなく、呼吸が神経系や代謝、感情の調整に深く関わっていることを示す、生理学的にも裏付けられた事実です。
特に「吐くこと」に意識を向けることで、副交感神経が優位になり、身体が安心と回復のモードへと切り替わります。
その状態では、集中力が高まり、判断力や柔軟性、そして身体の動きそのものにも変化が現れます。
普段無意識に繰り返している呼吸という行為に、ほんの少し意識を向けるだけで、
自分の体や心の状態に気づきやすくなり、習慣や選択にも良い変化が生まれるかもしれません。
「呼吸を整えることは、自分自身を整えること」。
その第一歩として、今日の一呼吸を丁寧に味わってみてはいかがでしょうか。
『BREATH 呼吸の科学』は、呼吸の重要性とその科学的背景を探求した一冊で、日常生活や運動における呼吸の質を見直すきっかけを提供します。
詳細や購入については、以下のリンクをご参照ください。
この本を通じて、呼吸の深さや質が私たちの健康や意識にどのように影響するかを学ぶことができます。
過去の記事はこちら